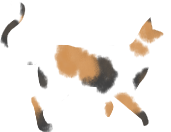
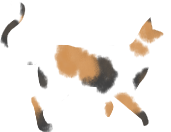

試し読み
一
けたたましい
どん、と背中が何かにぶつかる。
びくっと肩を震わせて振り返ると、そこにいたのは座敷童の
「相変わらず烏苦手なのな、お前。大丈夫か?」
櫂に気遣うような視線を向けられ、何だか急に気恥ずかしさが込み上げてくる。あたしの方がお姉さんなのに心配されていると思うと悔しくなって、あたしはぷいとそっぽを向いた。
「べ、別に怖くないもん。ちょっとびっくりしただけだもん」
「そう強がるなって、猫が烏を怖がるのは本能だろ」
「だ、だから怖がってなんかな……ひえっ!」
ニヤニヤとからかうような笑みを浮かべる櫂に反論しようとしたところで、窓の外の烏たちが一際大きな声を上げた。思わず小さな悲鳴を上げて、櫂の背後に隠れてしまう。ハッと気がついて顔を上げると、一層意地の悪そうな笑みを浮かべた櫂と目が合った。
「ほら、やっぱり怖いんじゃねえか」
したり顔で笑う櫂に、あたしはむっと口を尖らせる。悔しいけれどその通りだった。化け猫と言っても猫は猫である。櫂の言う通り烏を恐れるのは猫の本能であって、決してあたしが怖がりだということではないのだ。決して!
そう心の中で言い訳をするあたしをよそに、櫂は窓を開け放って外の様子を眺めていた。呑気なもので、空を飛び交う烏たちを見上げて「おー、こりゃすげえ」なんて感嘆の声を上げている。「烏が入ってきちゃうから早く閉めて!」と急かすと、櫂は「はいはいわかりましたあ」と茶化すように言って窓を閉じた。
ほっと一安心したあたしの隣で、櫂は独り言のように呟く。
「何かあったのかな。ただの烏なら何も珍しくねえけど、八咫烏だぜ。あいつらがこんなに慌てるって、普通じゃねえだろ」
「うん……そうだね」
そっと窓の外を覗きながらそろりと頷く。烏への恐怖心の方が
もしかして、と最近巷を騒がせている噂が頭をよぎる。櫂も同じことを思ったらしい、あたしが言うより先に、櫂の方がそれを口にした。
「巷で噂の祓い屋でも出たか」
祓い屋。妖を祓い清め消し去る力を持つ人間。あたしたち妖が最も恐れる相手であり、天敵だ。その祓い屋が近頃この近辺で活発に活動していると、専らの噂なのである。
最初はただの噂にすぎないと思った。けれど、今日はどこで誰がやられた、昨日はあいつがいなくなった、なんて話を次々に耳にするようになり、それは次第に現実味を帯びた不安となってあたしにのしかかってきた。
あたしはしがない一匹の化け猫。妖としては大した力を持っていない。つまり、弱い。祓い屋の手にかかれば、抵抗する間もなく一瞬でお陀仏だろう。野良猫よろしく気ままに外をふらふらしながら今まで過ごしてきたけれど、いつ祓い屋に出くわすとも限らない状況が怖くなったあたしは、櫂がいるこの屋敷に居候させてもらうことにしたのだった。(彼も勝手に人間の屋敷に住みついているだけなのだから、居候のようなものだけれど)。
「うーん、ここからじゃ何が起きてんのか見えねえな。見に行きてえけど、俺、屋敷から離れらんねえし……よしみけ、お前見に行ってこい」
「はあ!? 冗談言わないでよ!」
「冗談だって、いてて引っ掻くな!」
笑えない冗談を言う櫂の手に自慢の爪で引っ掻き傷を一つお見舞いした。「この凶暴猫め」なんて櫂は文句をたれているけれど、今のはどう考えても櫂が悪い。怖がっている、仮にも女の子に様子を見てこいだなんて。こういうところが櫂の残念なところだ。悪い人ではないのだけれど。
「けど、その祓い屋もこのご時世に熱心なことだな」
早くも
「ほっといたって、そのうち消えてくってのによ」
ぽつんと、寂しげに空に消えたその一言。
そうなのだ。
あたしたち妖は、わざわざ祓わずともいずれ消えゆく運命にある。妖という存在そのものが消えてなくなるのだ。そう遠くない未来に。どうしてと言われても、時代の流れと言うほかない。およそ半世紀前に端を発した目覚ましい文明の発展で、この国の人々の価値観は大きく変わってしまったらしい。「科学」に裏打ちされたものだけが正であり、合理的な説明のつかない不確かなものは否定される世の中になってしまった。
あたしたち妖の存在は、今この文明化された時代を生きる人々にとっては「あり得ないもの」。
あり得ないものは、存在しない。
そうして誰もが「妖」というものを忘れ去ったとき、あたしたちの存在は消えてなくなるのだろう。そんな滅亡の運命が見えているあたしたちにとってみれば、今頃になって妖退治に精を出している祓い屋の存在は滑稽であり、皮肉だった。
それでも。明日があるかもわからぬ身でも、あたしたちは目の前にある今このときを生き抜いていく。
だってまだ、生きているのだから。
二
櫂が住みついているこの屋敷は華族の豪邸だ。見ただけで大層なお金持ちだとわかる家で、旦那さまと呼ばれている男の人とその奥さん、一人娘のお嬢さま、そしてたくさんの使用人さんたちが暮らしている。櫂がいつからここに住みついているのかは知らないけれど、この屋敷の軒下で昼寝をしていたあたしに櫂が声をかけてきたのがきっかけであたしたちは知り合った。
座敷童の櫂はここで住人たちに悪戯をして困らせたり驚かせたりするのが楽しみだったらしいけれど、近頃は人間たちの反応がほとんどないという。それは間違いなく、妖が世間から忘れ去られつつあることの証だろう。あたしや櫂が目の前にいても、彼らの目には何も見えていないのだ。そのおかげであたしはこうして堂々と居候することができているのだけれど、やはり人間に存在を認識されなくなるのはもの寂しいものだった。
台所から難なくくすねてきた鮎の塩焼きを頬張りながら、静かになった空を見上げる。ギャアギャアとけたたましい声を上げていた八咫烏たちはどこかへ逃げ去ったのか、その姿はもう見えなかった。結局彼らに何があったのかはわからないままだと腑に落ちない気持ちでいると、「チチチッ」という鳴き声と共に小さな鳥が窓の外に現れた。
夜雀のコトヨギさんだった。
「まあ! 何であんたがここにいるのよ」
コトヨギさんはあたしの姿を見るなり露骨に嫌そうな顔をした。当然いい気はしないけれど仕方がない。コトヨギさんは雀で、あたしは猫だ。あたしが烏を恐れるのと同じように、雀である彼女にとって、猫のあたしは天敵中の天敵なのだから。
今はここに居候させてもらっている旨を、かいつまんでコトヨギさんに説明する。と、同じく台所から夕飯をくすねることに成功したらしい櫂が海老の天ぷらを持ってこちらにやって来た。
「あれ、コトヨギさんじゃねーっすか。何か用すか?」
「もう、呑気なものね。あなたたちも気づいたでしょう? さっきの八咫烏たちの大騒ぎ」
「ええ、そりゃもう。何があったのかコトヨギさん知ってます?」
「祓い屋よ! 祓い屋が出たのよ!」
「!」
コトヨギさんの口から出たその言葉に緊張が走る。口の中の鮎の味が急になくなった。
話には聞いていたけれど、本当にもう、いつ祓い屋に出くわしてもおかしくないのだ。そう思うとぶるりと背筋が震えた。
「……で? どうなったんすか、八咫烏たち」
つい一瞬前までの気の抜けた顔とは打って変わって、険しい顔をした櫂がコトヨギさんに問う。コトヨギさんも、事の深刻さを物語る声色で答えた。
「多くは逃げられたみたいだけど、何匹かは祓われてしまったみたい……」
「逃げた……ってことは、八咫烏が群でかかっても敵わねえ相手だったっつーことですよね。それじゃ俺らなんか瞬殺じゃねーっすか」
「そうよ。だから逃げるしかないわ。私はそれを伝えに来たのよ」
情報通のコトヨギさんらしかった。普段は人の噂話ばかり言いふらしている人だけれど、今回は皆に危険を知らせて回っているらしい。(ここにあたしもいるとは思っていなかったみたいだけれど)。
コトヨギさんは告げるべきことを告げると忙しなく飛び去っていった。また次の誰かのところへ危険を告げに行ったのだろう。残されたあたしは味のしなくなった鮎を何とか喉の奥に押し込み、神妙な面持ちの櫂を見やった。
「櫂、どうしよう。逃げろって……」
今すぐにでも、逃げるべきなのか。でも、逃げると言ってもどこに行けばいいのか。そんな不安を込めたあたしの問いを受けた櫂は、場違いにもへらっと笑って言った。
「おいおい、忘れたのか? 俺は座敷童だぜ。人間の家に憑く妖。この家からは離れらんねえ」
「あ……」
「まあ離れられたとしても今すぐ逃げる気はねえな。下手に外うろつくより家の中にいた方が安全だろ、祓い屋だって人んちに勝手に上がり込んではこねえだろうし」
「そ、そっか……そうだよね」
一瞬、櫂はこの場から逃げられないということに背筋が凍るような思いがした。けれど、そのあとに続いた言葉にほっとする。その通りだ。どこへ逃げれば安全かもわからないまま外に飛び出すより、ある意味人間に守られていると言えるこの場所にいる方がはるかに安全である。そもそも自分がここに居候させてもらうことにしたのもそういう理由からだったと思い出し、むやみに焦った自分が少し恥ずかしくなった。
そんなあたしの心中を察したのか、櫂はまたニヤニヤと意地の悪い笑みを浮かべて言う。
「別にお前が逃げたいなら俺は止めねえけど?」
「もーっ、わかって言ってるでしょ! やめて!」
「いってえ! そうやってすぐ引っ掻くのやめろよな!」
「櫂が意地悪なこと言うのが悪いんだもんっ」
ふんっ、とそっぽを向いて、食べかけだった鮎の塩焼きにかぶりつく。なくなっていた味は、いつの間にか戻っていた。
海老の天ぷらを平らげた櫂がまだ食べ足りないと言って台所へ向かったので、あたしもあとをついていった。旦那さまたちの食事はもう終わったらしく、台所では女中さんたちが後片づけをしている。食べ物を失敬するには少し遅かったようだ。ちぇ、と櫂が舌を鳴らす。なおも往生際悪く何か残ってはいないかと台所を物色する櫂のすぐ隣で、あたしたちの姿などまるで見えていない女中さんが思いがけない言葉を口にした。
「そろそろかしらね、祓い屋さんがいらっしゃるの」
あたしも櫂も弾かれたようにその女中さんに目を向けた。祓い屋。確かに今そう言った。まさかこの女中さんにはまだ妖の姿が見えているのかと一瞬焦ったものの、見たところ目の前にいるあたしたちに気づいている様子はない。そのまま、何事もなく話を続けている。
「旦那さまも奥様も妖怪の類は信じていらっしゃらなかったはずだけれど、どうして急にお祓いなんて……」
「あら、信じていらっしゃらないのは本当よ。でもほら、先週から働き始めた
「そうなの? 私は何も感じないわ……気のせいじゃなくて?」
「旦那さまもそう思ってらっしゃるみたいだけれど、これで辞められちゃったり外で変な噂をたてられても困るじゃない? だから幾代ちゃんを安心させるためっていうのが一番の理由みたいよ」
「ああ、そういうことなのね」
「ああそれと、あなたは知らないわよね。……あまり大きな声で言えないのだけど、この家、数年前にご長男が失踪されてるのよ。今はこの話は禁句になっているのだけど……本当に忽然と姿を消したものだから、神隠しじゃないかってみんな言っているのよ。幾代ちゃん、それも気になっちゃってるんじゃないかしら」
「まあ、そうだったの……それは知らなかったわ」
女中さんたちの噂話。この家に長男がいたことも、その長男が数年前に失踪していたことも、あたしは初耳だった。まさか櫂が何かしでかしたのか、と思わず彼を見やる。と、彼は呆れ顔でため息まじりに答えた。
「馬ァ鹿、俺にそこまでやる力ねえよ。俺がこの屋敷に来たときにはもういなかったぜ、そのご長男は」
「だよねえ。じゃあ櫂が来る前にほかの妖がいたのかな。ここ、好かれやすい家なのかもね」
「かもな。……ってそれどころじゃねえ! 祓い屋が来るってマジかよ!」
櫂がそう声を上げたと同時に来客を知らせるベルが鳴り響いた。「いらしたみたいね」と、女中さんが顔を見合わせている。そこまで来てようやくあたしも血の気が引いた。
祓い屋がここに来る? 否、もう来た?
下手に外に出るより家の中にいた方が安全だとつい先刻安心したばかりだというのに、まさか住人自ら祓い屋を招くとは。どうすれば、とおろおろするあたしの手を櫂が引っ掴む。そして、有無も言わせず走り出した。
「こ、櫂、どうするの!」
「どうするもこうするもねえだろ! 逃げるんだよ!」
「で、でも櫂は……っ」
櫂は座敷童だから。屋敷の外には出られないと、先ほど自分でも言っていたはずだ。逃げると言ってもどこへ行こうと言うのだろう、いくらこの屋敷が広いとは言え限界がある。一体どうするつもりなのかと不安を募らせるあたしを連れ、櫂は裏口の戸を勢いよく開け放った。
「ほら、ここから逃げろ」
掴んでいた手を離し、櫂はどんとあたしの背を押した。もしや、と彼を振り返る。彼はあたしの言いたいことがわかっているのか、少し困ったように笑った。
「ほら、早く行けって」
「そ、そんな……だって櫂は……」
「言ったろ、俺はここから離れらんねえ。お前一人で逃げろ」
「や、やだよ……あたしも残る!」
「馬鹿、八咫烏が敵わなかった相手だぞ? お前なんかまず助からねえよ」
「それは櫂だって一緒じゃん!」
「んなこと言ったってどうしようもねえじゃねえか」
そう言う櫂は
そんなあたしの心を知ってか知らずか、櫂はぽんとあたしの頭に手を乗せて言う。
「どうせ近い将来消える運命なんだ。今消えたって大差ねえよ」
「……っ、そんな勝手なこと言わないで!」
あたしの頭を撫でていた櫂の手をバシッと払いのける。これには櫂も驚いたのか、目をパチッと見開いてこちらを見た。彼の着物の襟を掴み、ぐいっと目一杯こちらに引き寄せる。そのびっくり眼を、あたしはキッと睨みつけた。
「今消えたって大差ない? あるよ! 少なくともあたしにとっては!」
何もわかっていない櫂を怒鳴りつける。本当に無神経な男だと思った。いつ消えようが変わらないなんて、そんな風に思えるのは本人だけだ。こんな風に自分だけ逃げ
けれど、と思う。実際、櫂の言う通りどうしようもないのだ。あたしも櫂も祓い屋に対抗できるほどの力は持っていないし、櫂が座敷童である以上、逃げられるのはあたしだけ。
櫂と一緒にここに留まり、一緒に祓われるか。
櫂を見捨てて、自分だけ逃げ延びるか。
本当はわかっているのだ。櫂が後者を選んでいるのはほかでもない、彼の優しさなのだと。あたしのことを想っているからこそ、そんな勝手な選択をするのだと。だからこそ何もできない自分が情けなくて、悔しくて、涙が出た。
「おいおい、泣くなよ。お前そんなしおらしい女じゃねえだろ?」
「……ほんっとに……失礼なんだから……」
つい先程払いのけた櫂の手をとり、両手でそっと包み込む。あたしより少しだけ大きなその手は小さく震えていた。
どうしてそんなに落ち着いているのか、なんて。そんなの、あたしの勘違いだった。
櫂だって、怖いのだ。怖いのに、あたしだけでも逃がそうとしてくれている。そんな櫂は、無神経な男でも失礼な男でもなかった。
「こずえ、ごめんね、ごめんね……っ」
こんな仲間思いの優しい友人を見捨てるしかないことに、申し訳ない気持ちが溢れて止まらない。ごめんねごめんねと何度も繰り返すあたしに、それでも櫂は笑ってくれた。
「だあから泣くなっつってんだろ。ほら、見つかる前に早く行け」
「あのね、あのね櫂……っ」
ごめんねと同じくらいに、否、それ以上に、伝えたい言葉がある。それを口にしようとした瞬間、ドタドタと慌ただしい足音が近づいてきたかと思えば、背広姿の初老の男性が猛然とこちらに向かってきた。
その手には、
「見つけましたぞおおおおおお!」
「ちっ、歳のわりに目敏い
「こ、櫂!」
嫌な力を宿した御札がこちらに飛んでくる。足が竦んで動けないあたしを、櫂がドンと突き飛ばした。突き飛ばされたあたしが尻餅をつくよりも早く、裏口の戸がバタンと閉まる。間髪入れずにカッと眩い光が戸の隙間や窓から溢れ出し、あまりの眩しさにあたしは思わず目を瞑った。
それは本当に、一瞬の出来事。
次に目を開けたときには、何事もなかったかのように平穏そのものの景色が広がっていた。
「こ……こずえ……」
ぽつりと、彼の名前が口から漏れる。祓い屋はまだすぐそこにいるのだから逃げなければと思うのに、あたしは尻餅をついたまま茫然とその戸を見つめていた。
こんなに、こんなに呆気なくお別れだなんて。
一番伝えたかったことを、まだ伝えていなかったのに。
泣いている場合じゃないとわかっていても、大きな後悔が押し寄せてくる。大切な友人一人を失った悲しみは、覚悟していた以上のものだった。
でも、こうしてあたしを逃がしてくれた彼の厚意を無下にするわけにはいかない。そう自分を奮い立たせ、震える膝で何とかあたしは立ち上がった。
まさに、そのとき。
「いってええ……」
いやに低い、櫂の声が聞こえた。
聞き慣れた彼の声とはまるで違う。けれどあたしはそれを櫂の声だと思った。もちろん、先ほど現れた祓い屋のお爺さんの声とも違う。これは、櫂の声だ。
そう確信するや否や、考える間もなく体が動いた。あたしと櫂を隔てる戸に飛びつき、がちゃりと取っ手を回す。躊躇うことなく、あたしはその戸を開け放った。
目に飛び込んできたのは、学生服を着た男の人の後ろ姿。
櫂じゃない、と混乱したのも束の間。ものすごい勢いでこちらを振り返ったその人の顔にはどこか見覚えがあった。
「こ……櫂……?」
つい先ほどまで一緒にいた櫂とは明らかに違う。けれどその顔は確かに櫂の面影を
「大人になった櫂」のような彼を見上げ、ぽかんと呆けるあたし。そんなあたしとは正反対の切羽詰まった様子で、彼はあたしを叱りつけた。
「馬鹿! 何で戻って来やがった!」
「だ、だって櫂の声がして……っていうか、櫂……? 櫂なの?」
「はあ!? 何言って……、ん!?」
ようやく何かおかしいことに気づいたらしい彼。何かを確かめるように、自分の体をあちこち見回している。そうしてあたしに視線を戻したあと、最後に、祓い屋のお爺さんに目を向けた。
黙ってお互いを見つめ合う二人。
先に沈黙を破ったのは、祓い屋のお爺さんの方だった。
「
「………、はい」
「……え?」
目の前で交わされたたった一言の会話に動揺が走る。
頼成、櫂?
頼成って確か、この屋敷に住んでいる一家の名前じゃ……。
そこまで考えたところで、先ほど聞いた女中さんたちの会話が脳裏を過ぎった。
――数年前にご長男が失踪されてるのよ。
――本当に忽然と姿を消したものだから、神隠しじゃないかってみんな言っているのよ。
女中さんたちの噂話と、目の前で起きていることがすべて繋がっていく。
数年前に忽然と姿を消した頼成家の長男。
その屋敷に住みついていた、同じ「こずえ」という名前を持つ座敷童。
座敷童の櫂が祓われて、代わりに現れた人間の頼成櫂。
頼成櫂に重なる、座敷童の櫂の面影。
そこから導き出される答えは、
「櫂……、人間……だったの…?」
人間に祓われた妖が人間になったなんて話は聞いたことがない。けれどそうとしか考えられなかった。どういう理屈かと訊かれてもわからないけれど、今目の前にいるこの青年は、間違いなく櫂だ。それだけは絶対の確信があった。
あたしの問いかけに、一瞬言葉を詰まらせた櫂。やがて彼は、観念したかのような深いため息と共に頷いた。「そうだよ、」。
「いつの間に座敷童なんかになったのかわかんねえけど……俺は頼成櫂。この屋敷に住んでる頼成家の長男で、――人間だ」
「……そんな、ことって……」
「ふむ、思った通りですな! もう一人いたのは予想外でしたが」
「!」
黙ってあたしたちのやりとりを眺めていた祓い屋のお爺さんが、ずいっとこちらに一歩踏み出した。未だに事が信じられないあたしと違い、大いに納得したような顔をしている。櫂がサッとあたしを自分の背後に隠した。
そうだ。櫂が人間になったとか何とかですっかり忘れかけていたけれど、このお爺さんは妖退治に来た祓い屋で、あたしは逃げなければならなかったのだ。一度どこかへ飛んでいった恐怖心と危機感がまた一気に湧き上がってきた。
また一歩、お爺さんがこちらに踏み出そうとする。
と、やけに鋭い櫂の声がそれを制止した。
「爺さん。こいつには手出させねえぞ」
そう言う櫂の手は震えてはいなかった。祓われる恐怖を押し殺してあたしに逃げろと言った、小さな座敷童の櫂とは違う。あたしを守ろうとするその背中は、ずっとずっと大きくなっていた。
瞬きをする隙もないような、櫂とお爺さんの睨み合い。それはそう長くは続かず、今度はお爺さんの方が観念したように言った。
「その化け猫のお嬢さんを大切にしているようですな」
「ああ」
「ふむ……それならば、或いは……」
「……?」
何やら一人でぶつぶつと呟きながら、何かを思案するお爺さん。
やがて答えが出たのか、お爺さんはくるりとこちらに背を向けて言った。
「私は祓い屋だ。
「…! 嘘じゃねえだろうな爺さん」
「これこれ、年長者に向かってなんちゅう口の利き方を……。まあよい。嘘ではありませんぞ」
きみのその気持ちが、嘘にならんのならね。
そんな含みを持った言葉を残して、祓い屋のお爺さんは去っていった。
「助かった……の、かな……」
「……みたいだな」
お爺さんの姿が完全に見えなくなり、どちらからともなく安堵の息をつく。しかし、ほっと気持ちが落ち着いたはほんの一瞬だった。
櫂が人間って、どういうこと?
本人もそれを問われることがわかっているのか、何やらバツが悪そうに苦笑いを浮かべている。隠しごとがバレたというよりは、本人もどう説明すればいいのかわからず戸惑っているような顔だった。
改めて、
「えーと……俺もどういうことなのかいまいちよくわかってねえんだけど」
戸惑いつつも説明をしようと、櫂がそろそろと口を開く。本人もわかっていないものをあたしが理解できるかわからないけれど、彼の言うことならばあたしは信じようと思った。
彼は、体を張ってあたしを守ってくれた人なのだから。