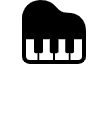
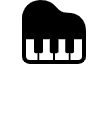

試し読み
一
雲一つない青空と、満開の桜。絶好の入学式日和のこの日に、わたしは大学に入学した。子供の頃からの夢であるピアニストになるために選んだ、音楽大学に。きっと同じものを目指しているであろう同輩たちの中にはわたしよりも演奏の上手い人がたくさんいるだろうと思うと少し畏縮してしまいそうだけれど、それでも負けずに精一杯やっていこうと気持ちを新たにした。
「おー、みやちゃん。お疲れ」
「あ、由くん」
入学式を終えてまだ見慣れないキャンパスの中を歩いていると、見知った顔が声をかけてきた。二つ年上の従兄、一ノ宮由渡くんだ。由くんもこの大学に通っていて、同じくピアノの演奏を専攻している。わたしがこの大学を選んだのは由くんがいるからであり、そもそもわたしがピアノを始めたきっかけも由くんだった。由くんのお母さん──つまり伯母さんがピアノ教室を開いていて、由くんも昔から当然のようにピアノを弾いていたから、それを見て自分も弾いてみたいと思うようになったのだ。だから、大学選びには少しも迷わなかった。
「由くん、入学式で代表演奏するならそう言ってよー! びっくりしたじゃん」
そう言って笑いながら、由くんに駆け寄る。由くんは何食わぬ顔で「別にいちいち報告するほどのことじゃないと思って」と笑った。
先ほど行われた入学式の様子を思い出す。学長の話や新入生代表の挨拶が終わったあと、音大らしく在校生による演奏の披露があった。それは各専攻ごとに選ばれた代表者による演奏だったのだが、ピアノ専攻の代表として舞台に立っていたのは由くんだったのだ。代表による演奏と聞いたときにもしやとは思ったものの、実際に舞台の上にその姿を見たときはやはり「まさか自分の知っている人とは」と思ったものだった。
「報告するほどのことでもないってねえ……あとで聞いたけど、あれ各専攻の首席が選ばれるって話じゃん……」
「まあ、そうらしいね」
「首席って普通四年生なんじゃ…?」
「そうだね」
「それを予告するほどのことでもないって言っちゃうところが由くんだよねえ……」
由くんの実力はわたしもよく知っている。子供の頃から彼は天才と称されていた。十九世紀の作曲家かつピアニストでピアノの魔術師と呼ばれたフランツ・リストの再来と騒がれ、クラシック業界の中では彼の名を知らない者はいないと言っても過言ではないほどだ。何せコンクールに出れば一位以外をとったことがない。だからさぞかし立派な音大や芸大に進むものだと思っていたら、由くんが選んだのは名門とは言い難い弱小音大だった。スカウトもたくさんあっただろうにどうしてと一度訊いたら、由くん曰く「長距離通学が面倒くさい」とのこと。この大学を選んだのは自宅から一番近い音大だったからという安直な理由らしかった。そんな彼が数々のコンクールで優勝の座を総なめにしているのだから、世の中はなかなか理不尽である。
「なんか、由くんそのうち刺されそうで心配だわ」
「何それ」
「前から“練習もろくにしないくせに”ってよく陰口言われてたじゃん……小学生のときは“ピアノ星人”とか変なあだ名つけられてたよね」
「そういやそんなこともあったね」
「さっき入学式で『魔王』弾いてたからもう新入生の間で“魔王”って呼ばれてるよ。まああんなすごい演奏聴かされたら魔王と言いたくもなるけど……でも入学式で『魔王』ってどうなの。選曲のセンスを疑うよ」
「いやあ、なんか俺陰で魔王って呼ばれてるみたいだから応えてあげようかなって」
「既に呼ばれてたんだ……」
「っていうのが一パーセントで」
「残りの九十九パーセントは?」
「三連符叩きたい気分だった」
「ほぼ気分じゃん! 相変わらずだねえ……」
相変わらず奔放な従兄に少々呆れる。けれど、身内の贔屓目かもしれないが、それでこそ一ノ宮由渡だと思ってしまうのが正直なところだった。
由くんの演奏はもはや人間業ではない。そんな演奏を平然とやってのける彼を“魔王”と称したくなるのも無理はないと、ざわつく入学式の会場でわたしは一人納得していた。
そして、その“魔王”が自分のよく知る人であることが、わたしは少し、誇らしいのだった。
二
それからしばらく大学生活を送って実感したのは、やはり、由くんは学内でかなりの有名人だということ。
その理由はもちろんピアノの腕前にあるけれど、耳に入ってくるのはあまり芳しい噂ではなかった。と言うのも、由くんはあれほどの実力を持っていながらあまり練習熱心ではない。それだけでも妬まれるには十分すぎるのに、おまけにCDデビューの話やメディアからの取材、超有名楽団からの共演依頼など、演奏家を目指す者なら誰もが羨むような誘いをほとんど蹴ってしまうのだ。それも、「面倒くさい」という軽薄な理由で。おかげで「一ノ宮はピアニストとしては頂点を極めているが人間性は底辺だ」と言われるあり様だった。
今までも似たようなことを言われていたのは知っていたけれど、学校中で噂されるほどではなかった。しかしここは音大という本気で音楽の道を志している人が集まっている場所だ、だから余計に反感を買ってしまうのだろう。けれど本人はどこ吹く風だった。
由くんはピアノに関して“弾くこと”にしか興味がない。
だから、CDデビューも取材も共演もすべて「面倒くさい」のだ。上手く弾きたいと思っているわけではないから練習もしない。上手い下手を判断しているのは他人であって、彼は“ただ弾いているだけ”なのだ。天才とはまさにこのことであり、凡人がそれを妬むのはある意味当然のこと。おまけに少々口が正直すぎると来れば、そんな噂を立てられるのも無理はなかった。
そう頭では理解していても、やはり身内のことを悪く言われるのはあまり気分のいいものではない。
けれど、だからと言って彼を擁護する勇気がわたしにあるわけでもなかった。新たにできた友人に「わたしは“魔王”の従妹だ」と言えずにいることが何よりの証拠だ。わたしと由くんは苗字も違うし、同じキャンパス内にいると言えど学年が違えば会うこともあまりない。だから黙っていればわからないだろうと、わざわざ自分から言い出す必要もないだろうと、そんな風に思っていた。
その由くんから「財布忘れたから昼メシ代貸して」とラインでメッセージが送られてきたのは、入学から二ヶ月ほどが経った頃のこと。少し迷ったものの、いくら関係を隠していると言っても由くんを避けたいわけではないので、わたしは昼休みに彼と会う約束をした。
由くんが待ち合わせ場所に現れたのは、昼休みに入ってだいぶ時間が経ってからだった。
「ごめん遅くなって。教授に捕まってた」
そう言って現れた由くんは心底うんざりした顔をしていた。余程教授に長々と付き合わされたのだろう。ちょうどお昼時でお腹もすいているところだろうし、余計に煩わしかったに違いなかった。
「何で捕まってたの?」
「なんか教授の友達が主催してる楽団のコンサートにゲストで出てくれないかって、しつこいの何の」
「へえ。出るの?」
「出ないよ」
「うん、だろうと思った」
愚問だった。由くんは好きでピアノを弾いているけれど、誰かのために弾いたりはしない。ただ自分が弾きたいから弾いているのだ。だからそういった演奏を披露する機会も、気が乗れば出るし乗らなければ出ない。プロのピアニストとして活動しているわけではなく、それでいて絶対的な実力があるからこそできる奔放な選択だった。
「みやちゃんがいなかったら昼メシ抜きになるところだったよ」
「ええ……わたしのほかに貸してくれる人いないわけ?」
「友達いないからね」
「ああ……」
納得の一言に閉口する。学内での由くんの評判を考えれば頷けた。
「あー、でも今からじゃ学食めちゃくちゃ混んでるよね……やだなあ」
「由くん人多いとこ嫌いだよね」
「みんなうるさいんだもん。耳に悪い。あんなの聞いてたら耳が腐る」
「そういうこと言うから友達いないんでしょうが」
「俺の耳は美しい音を聴くためにあるの」
「………」
事もなげに由くんの口から出てきた言葉にぎくりとした。
わたしの演奏も、由くんにとっては“美しくない音”なのではないか。わたし程度の、演奏では。
「あ、ていうか、うるさい以前に今からじゃ席空いてなくない?」
目の前の現実から目を逸らすように話題を変えた。既に昼休みも半分ほどが過ぎ、今から人だらけの学食に突撃して運よく席が確保できたとしても、注文するまでにしばらく並ぶであろうことを考えると時間内に食べきれるかどうかは怪しいところである。せっかくわたしからお金を借りても、結局昼食抜きになってしまいそうだった。
「あー、そうだよね。教授め許さん」
「あ、じゃあわたしのお弁当半分あげよっか。半分じゃ足りないと思うけどまったく食べないよりはマシでしょ」
「え、マジ? やった! 今度何か奢るよ」
「はは、よろしく」
わたしの提案に、目に見えて機嫌がよくなった由くん。色気より食い気ならぬ、ピアノより食い気だ。周囲が彼をどう評価しようと、やはり彼は昔からよく知る由くんだった。
三
次の日、弁当を分けてくれたお礼にと、由くんがケーキをご馳走してくれることになった。何でも、大学の近くにいい店があるらしい。入学から二ヶ月が経ったとは言えまだ周辺に何があるのか把握できていないわたしは、一体どんな店に連れていってくれるのだろうと朝からわくわくしていた。
授業を終え、由くんが四限目の授業をしていたという実習棟の教室へ向かう。実習棟はその名の通り楽器の演奏や歌唱の実技授業を行うための教室が集まった棟で、放課後には練習室として学生に貸し出されている。防音はそれなりにされているものの、中に入るとそこかしこから様々な音色が聞こえてきた。
入学したてでまだ実技授業の少ないわたしにはあまり馴染みのない棟を、由くんから聞いた教室を探して歩き回る。やがてどこからともなく聞こえてきた一つの音に、廊下中に溢れかえっていたその他の音たちはすべて意識の外へ出ていった。
姿が見えなくても、わかる。
これは、由くんの音。
この世のものとは思えないその音色に吸い寄せられるように、一つの教室にたどり着く。重たい扉をそっと押し開ければ、そこにいたのは思った通りの姿をした彼だった。
「お。来た」
「あ、……」
由くんはわたしに気づくとすぐに演奏をやめてしまった。もう少し、否、少しと言わず最後まで聴いていたかったわたしは、曲が終わるまで扉の外で待っていればよかったと後悔した。
「…なに? 呆けた顔して」
「……いや………聞き惚れちゃって……」
あまりの演奏に、感想の言葉などなくしてしまう。由くんの音は言葉をも通り越して聞く人の心を射抜いていくのだ。何ものをも凌駕する圧倒的な世界を奏でる─それが天才と言われる由くんの演奏だ。
けれども本人は「そう?」と事もなげな顔をして笑っている。それもきっと天才が故なのだろう。彼はきっと努力でこれを身につけたのではない。“ただ弾いているだけ”。神から授かった、天性の才能だ。そうとでも思わなければ、わたしたち凡人はどんなに努力しても追いつけないその演奏力に納得ができなくなってしまう。だからこそ人は彼を“天才”と呼ぶのだ。
「今の、『マゼッパ』だよね」
「うん」
「あれを、そんな軽やかに……はああ」
ため息が出るほどうっとりするということを身を以って知る。これが人間の出せる音なのかと、本気でそんなことを思ってしまう絶対的な音色だった。
フランツ・リスト作曲、『超絶技巧練習曲第四番「マゼッパ」』。わたしは弾いたことがないけれど、曲は知っている。難曲揃いと言われるリストの超絶技巧練習曲の中でも、一、二を争う難曲中の難曲だ。それをまるで息でもするかのようにさらりと弾きこなす由くんに、やはり“天才”以外の言葉は思い浮かばなかった。
「そうだ。みやちゃん、久しぶりに連弾しようよ」
「えっ」
「子供の頃よく一緒に弾いたじゃん?」
そう言って由くんは椅子をもう一脚どこかから持ってきて隣に並べた。予想だにしなかった誘いに動揺してしまう。一緒にと誘ってくれたことはもちろん嬉しいけれど、わたし如きが天才・一ノ宮由渡と連弾だなんて畏れ多いという気持ちの方が大きかった。子供の頃は何も考えずに一緒に鍵盤を叩いたものだけれど、今はもう、あの頃と同じではいられなかった。
「わ、わたしと一緒じゃ由くんやりにくいでしょ」
「なんで?」
「や、だって……わたしはそんな……由くんみたいに上手くないし……」
「別に上手い演奏したくて誘ってるんじゃなくてただ一緒に弾きたいだけなんだけど……まあ、みやちゃんがそう言うならいいや。無理に弾いても楽しくないもんね」
由くんはへらりと笑ってそう言った。共演を免れたことにほっとしたものの、気を遣わせてしまっただろうかと少し不安になる。けれど由くんの性格からしてそれはないだろうとすぐに思い直した。
由くんはきっと、わたしの演奏について上手いも下手も何も思っていない。
何故なら、“弾くこと”にしか興味がないから。“他人がどう弾いているか”なんて、彼の眼中にはないのだ。
「じゃあさ、代わりと言っちゃ何だけど一曲聞いてくれない? さっき途中でやめちゃったから」
由くんが再び席に着きながらわたしに言う。もちろんだ、むしろ聴きたいとわたしが返すと、由くんはやはりへらりと笑って鍵盤に向かった。
世界を壊すと言っても過言ではない音が、旋律となって鳴り響く。
しばらくすると、わたしと同じようにこの音に吸い寄せられたのであろう人たちが集まり始めた。演奏が進むにつれてその数は増えていったが、まるで見えない壁でもあるかのように少し離れた場所から遠目に様子を見ているだけだ。ピアノのすぐそばに立っている自分まで注目されているように思えてしまい、何だか緊張してきてしまった。
あの人たちが見ているのは、由くんだ。誰もわたしの存在など気にしてはいない。
そう、自分に言い聞かせている中で。わたしの耳は、聞きたくなかった言葉を拾い上げてしまった。
「あの女誰? 一ノ宮が教授以外の人と一緒にいんの初めて見た」
ああ、ほら。
わたしが“魔王”の関係者であることが、知れてしまった。
別に、だからと言って何が起こるわけでもない。ただ「あの人は魔王の知り合いだ」と噂されるだけだ。それなのにどうしてこんなにも絶望的な気分になるのか、その理由は自分でもよくわかっていた。
わたしは“魔王”の足元にも及ばない、少しピアノが弾けるだけの音大生。
そんな人間が天才・一ノ宮由渡の隣にいることを、人は何と言うだろう。
それが怖くてたまらなかった。
およそ七分の演奏が終わると、集まっていた聴衆たちはざわつきながらも蜘蛛の子を散らしたように去っていった。何だかんだと噂していても、結局“魔王”が怖いらしい。当の由くんは大勢の人に演奏を聴かれていたことなど歯牙にもかけていない様子だった。
これが、天才か。
それをまざまざと見せつけられたような気がして、わたしは畏縮してしまった。
「……ああいうの、嫌だ?」
唐突に、由くんから投げかけられた問い。何のことかわからず訊き返すと、由くんは、少し悲しそうな顔をして言った。
「俺のことで周りに何か言われるの、やだ?」
「あ……」
そう言われて初めて、由くんもあの言葉に気づいていたのだと知った。てっきり、誰に何を言われていようと由くんは耳に入れていないものだと思っていた。
きっと、言われているのが自分のことだったら由くんは何とも思わなかっただろう。
でも、わたしのことだから気にかけてくれた。
それを思うだけで、見ず知らずの誰かのたった一言で押し潰されそうになっていた自分が馬鹿らしく思えてきたのだった。
「…別に。気にしない」
少々不貞腐れた声で返事をする。あの発言を聞いたときはただ焦燥感ばかりが募ったけれど、今になって何だか腹が立ってきたのだ。
別に、わたしが何者だろうといいじゃないか。
由くんが誰と一緒にいるかなんて、そんなもの、由くんの自由だ。そしてわたしが誰と一緒にいるかだって、わたしの自由だ。ああ、どうしてあんな言葉を気にしてしまったのだろう。気にしたところで何の意味もないことだった。
わたしの返事を聞いた由くんは、まだ念を押すように言う。
「自分で言うのもあれだけどさ、俺あんまり評判よくないから、一緒にいるとこれからも何かいろいろ言われると思うよ。嫌だったら学校ではあんまり絡まないようにするけど、大丈夫?」
「平気。別に由くんが気を遣うことじゃないじゃん?」
「そうだけど、この学校にいる限りどうしたって俺の影がついて回るだろ。人のことばっかりああだこうだ言うのが好きな下品な輩は一定数いるし」
「だからそういうこと言うから評判が……」
「まあみやちゃんが気にしないならいいんだけど。それじゃほら、ケーキ食べに行こ。お腹すいた」
何事もなかったかのように、由くんはすたすたと歩き出す。本当に、よくも悪くもマイペースすぎる人だ。でも、だからこそあのような演奏ができるのだろう。何ものにも囚われない、自分の世界をすべてぶちまけるような演奏が。
この日を境に、わたしと由くんは昼休みや放課後にちょくちょく会うようになった。